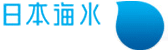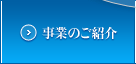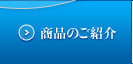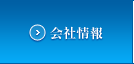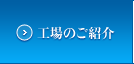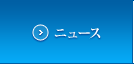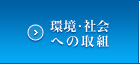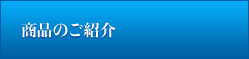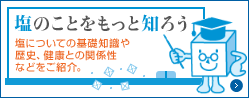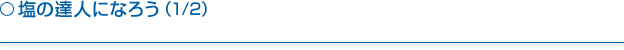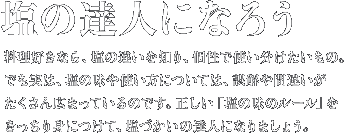HOME > 商品のご紹介 > 塩のことをもっと知ろう > 塩の達人になろう 1/2
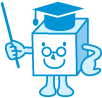
塩の味を決める大きな要因は「粒の大きさと粒形」。一般的に、粒の大きい塩ほどまろやかな味です。細かい粒は口の中で素早くたくさん溶けるため塩味が強くなり、大きな粒は口の中でゆっくり少しづつ溶けるのでまろやかに感じるのです。また、フレーク塩のように形状が複雑で比表面積の大きい塩は強く塩味を感じます。

大粒

小粒
「じゃあ『岩塩』や『天日塩』は味とは関係ないの?」と疑問に思われた方もいるかもしれません。実はその通りで、製法や原料は、あまり味とは関係ないのです。たとえば岩塩の味がまろやかなのは粒が大きいからで、細かいサラサラの岩塩ではそういう味はしません。にがりの量に関しても、単純に「この製法だから多い」ということはいえないのが実状です。
 特に日本では、天日塩を外国から輸入し、国産のにがりを添加した商品がたくさん販売されているので、にがりの含有量と製法の関係はあいまいです。つまり純粋に味覚の見地からいえば、やはり「粒の大きさ」「にがりの量」が味を決めていることになります。
特に日本では、天日塩を外国から輸入し、国産のにがりを添加した商品がたくさん販売されているので、にがりの含有量と製法の関係はあいまいです。つまり純粋に味覚の見地からいえば、やはり「粒の大きさ」「にがりの量」が味を決めていることになります。イメージに訴える広告などにまどわされず、目的に応じた塩を正しく選びたいですね。